「「死は終わった」彼は自分に言った「もはや死はない」
彼はひとつ息を吸い込み、吐く途中で止まったかと思うと、ぐっと身を伸ばしてそのまま死んだ。」
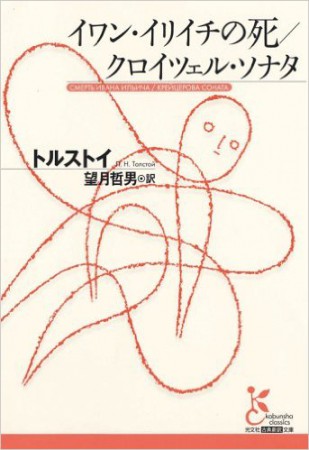 イワン・イリイチは病を得て考えます。
イワン・イリイチは病を得て考えます。
今までの人生を…
登っているように思っていたが、実は下っていた。
努力して判事となり、邸宅を構え、裕福な人のふりをしました。
そのような人の生活は皆似ているとトルストイは書いています。
なぜ、自分が病になり、苦しむのか?
その原因を探す愚。
人間は原因があると思ってしまう。
病気になる理由などないのです。それは、たまたま…
仮にあったとしても、回避できなかったのです。
懸命に漕ぐ理性の「櫂」が空を切ってしまいます。
理性の櫂に感情の「解」はないのです。
何名もの医師に診察を依頼しますが、原因はわからない。
しかし、彼等はなんとかしますと言明する。
そして続く効果のない治療
イワン・イリイチは最終的にその治療を拒否します。
農民出身の下僕のゲラーシムだけは家族にまして献身的に主人に仕え、正直でした。
イワン・イリイチに向かって「みんないつか死ぬのです。お世話するのは当たり前のことですよ。」
言いにくいことを主人に向かってはっきり言います。
イワン・イリイチはゲラーシムの言葉に救われます。
そして、ゲラーシムは夜を徹して主人の側に控えるのです。
イワン・イリイチは臨終の機にベッドサイドで泣く幼い息子に許しを請うことで光を見ました。
「ゆるしてくれ」というべきところ…その際、すでに彼には言葉が出ませんでした。
しかし、その言葉の後に、あれほどの痛みも消えてしまったのです。
イワン・イリイチの臨終の想いを現代の我々も同じように繰り返すのでしょうか。
自分の妻と子にさえ最後の気持ちが伝えられなかったイワン・イリイチ
トルストイが 1886年に残した本書と同じように。
齋藤真衡
